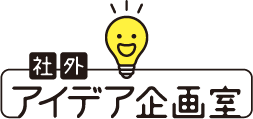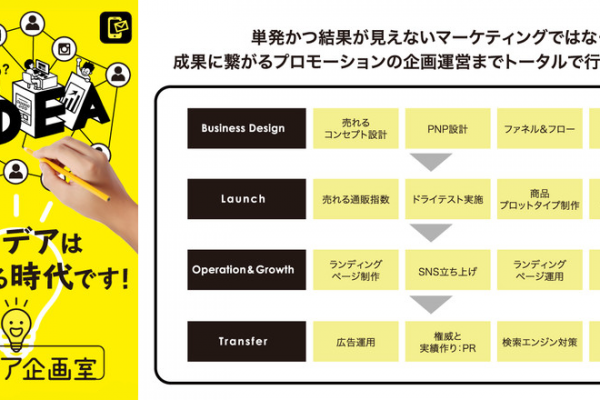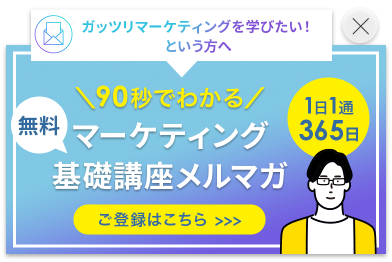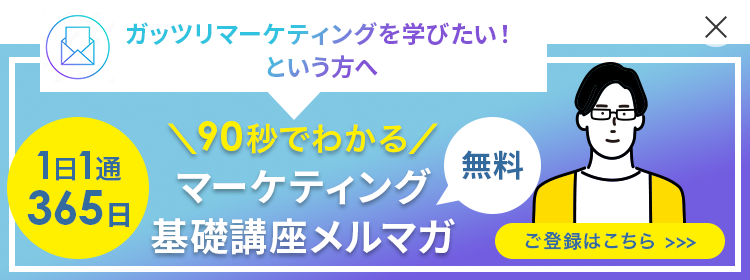そのサイト、アウトかも?ダークパターン規制と認証マーク導入の影響を徹底解説
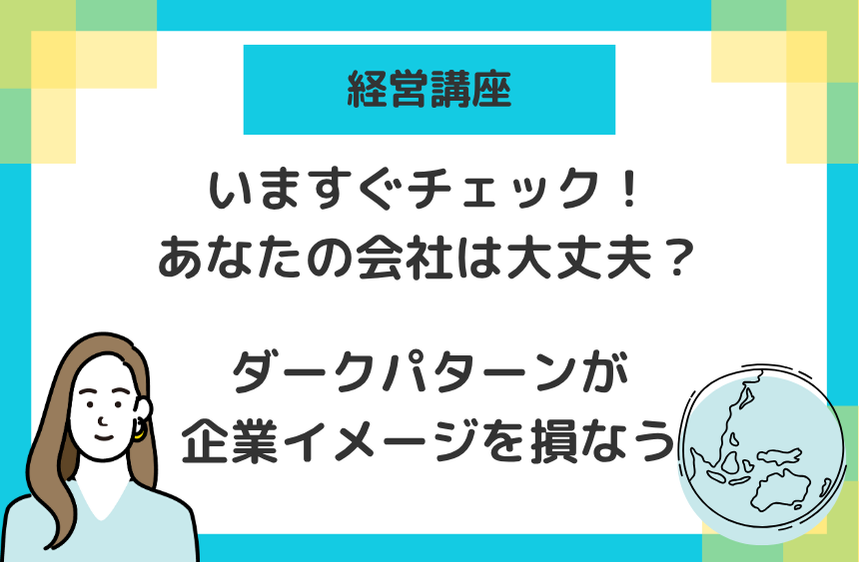
「ダークパターン」とは、ユーザーに不利益な選択を意図的に誘導するウェブデザインのこと。知らず知らずに利用してしまえば、事業者は信頼を失い、最悪の場合は法的リスクも発生します。
まもなく「非ダークパターン認証マーク」の制度が開始されるにあたり、事業者には正しい知識と対応が求められています。
本記事では、ダークパターンの具体例や注意点、今後の対応策をわかりやすく解説します。「自社サイトの仕様がダークパターンに該当していないか?」をしっかりチェックし、ユーザーに信頼されるサービス運営に役立ててください。
目次
ダークパターンとは?
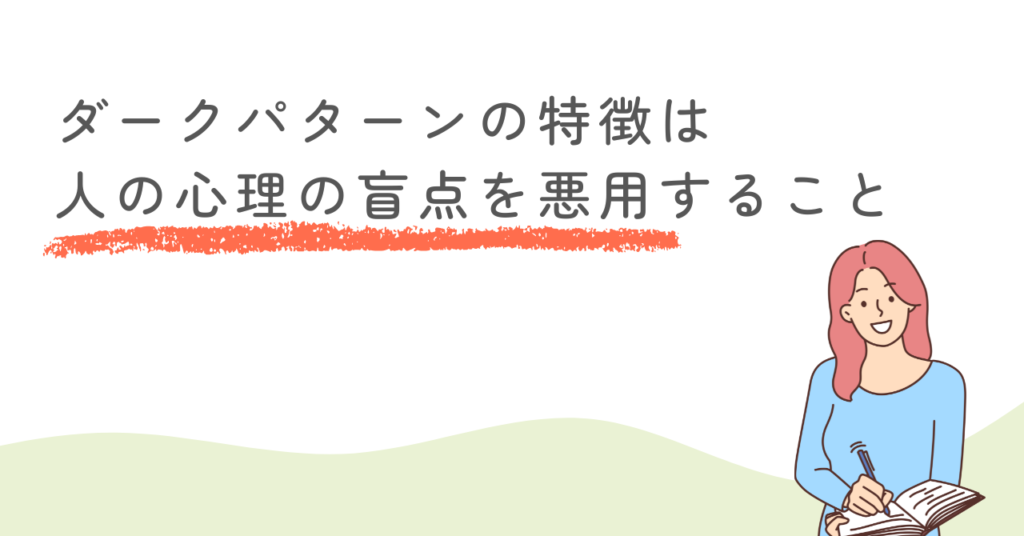
ダークパターンとはWebサイトやスマホアプリで、ユーザーをだまして企業に都合の良い行動をさせるデザインやしくみのことです。
例えば
- 無料だと思ってサービスに登録したら実は有料だった
- 解約しようと思ったらやり方がわからない
- 「現在⚪︎人が閲覧中です」と表示が出て、人気商品だと思った
- 勝手にいらない商品がカートに入っていた
など。
これらは一見すると上手な売り方に見えますが、実際にはお客さんをだます行為として世界中で問題になっています。
ダークパターンの特徴は、人の心理の盲点を悪用すること。大事な情報をとても小さな文字で書いたり、普通とは逆の動きをするボタンを作ったりして、間違った選択をするように仕向けます。
最近は、消費者を守る観点から世界各国でダークパターンへの規制が厳しくなり、違反した企業には巨額の罰金が科されるケースも増加。
日本でも規制への関心が高まり、企業は具体的な対策が必要になってきました。
今年開始の新制度とは
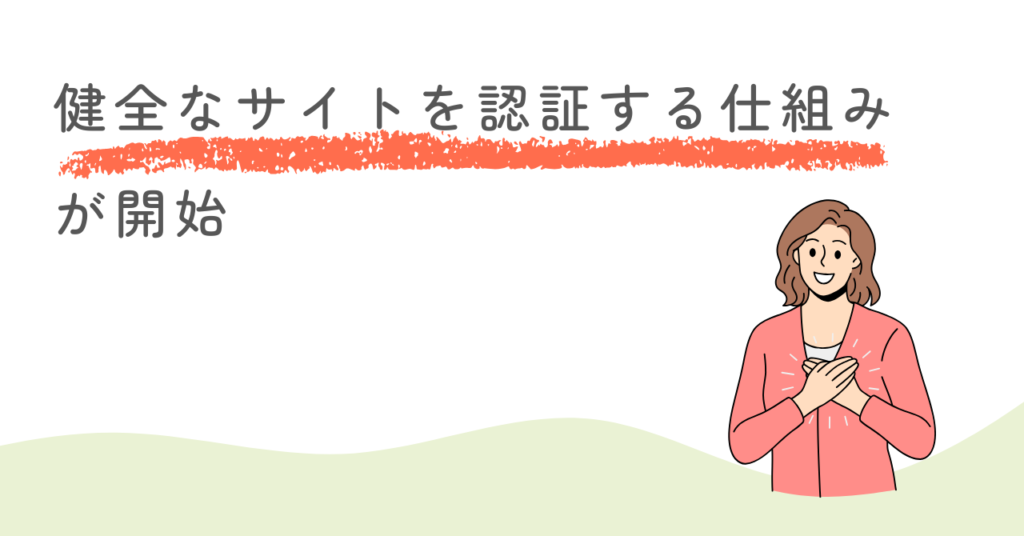
日本では、「一般社団法人ダークパターン対策協会」により、ダークパターンを使っていない健全なWebサイトを認証するしくみがまもなく始まります。
これは法律ではなく、業界の団体が自主的に作った認証制度。2025年1月にルールとチェック項目が発表され、7月から審査が開始。企業の自主的な取り組みを応援することが目的です。
制度の特徴は、単にルールを示すだけでなく、実際にWebサイトを調べて認証マークを出すこと。これにより、お客さんは信頼できるWebサイトを見分けることができ、企業も健全な運営をしている証明を得ることができます。
また、「ダークパターン通報窓口」も作られる予定で、消費者庁などとも連携する計画になっており、業界団体と国の機関が協力する体制も作られます。
今のところ強制力のある法律ではありませんが、将来的には法的な規制になる可能性もあり、企業は早めの対応が必要です。海外の流れを見ても、自主規制から法規制への変化は一般的で、日本でも同じような展開が予想されます。
この規制がEC・通販業界に与える影響は?

EC・通販業界は、ダークパターン規制の影響を最も強く受ける業界の一つです。
なぜならネット販売では、お客さんとの接点がサイトやアプリだけなので、売上を上げるために様々なデザインや売り方が使われており、その中にダークパターンに当てはまる方法が含まれている可能性が高いからです。
主な影響を受ける分野
月額課金サービスでは、「初月無料」の後に自動で課金が始まるしくみや、解約手続きをわざと複雑にすることが特に問題視されています。今後は
- 料金のしくみを分かりやすく示す
- 簡単に解約できるようにする
- 課金前にはっきりとお知らせする
などが必要になります。
買い物カート機能でも変更が必要になる可能性があります。
- 商品を選ぶときに関連商品を自動でカートに入れる機能
- 配送方法でより高いサービスを最初から選んでおく方法
などが見直し対象になります。
価格の表示方法も影響を受けます。
- 「在庫あと少し」「本日限定価格」などの急がせる表示
- 税込み価格を小さく表示する方法
についても、もっと分かりやすい表示が求められるようになります。
業界にとってのメリット
一方で、この規制は業界全体にとってもメリットがあります。
健全な競争環境ができることで、お客さんの満足度向上と長期的な関係づくりが可能に。また、認証を受けた企業は、お客さんからの信頼を得て、他社との違いを示すことができます。
お客さんとのトラブルが減ることで、サポートにかかる費用も削減できます。さらに、海外進出を考える企業にとっては、国際的な基準に合ったサイト運営のノウハウを早めに身に付ける機会にもなります。
ダークパターンを続けるとどうなる?
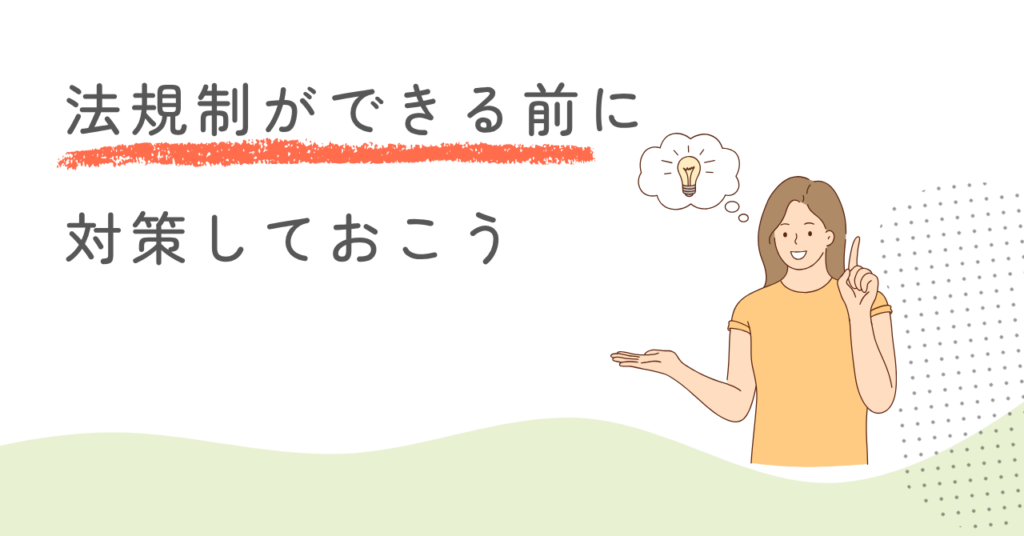
今の日本では、ダークパターンを直接規制する法律はありません。しかし、特定商取引法や景品表示法などの既存の法律で規制されるケースが増えています。
今ある法律での処罰
特定商取引法では、大事なことを教えないことや誇大広告が禁止されており、ダークパターンでこれらに当てはまる場合は営業停止や改善指示の対象になります。
景品表示法では、実際よりも良く見せる表示が禁止されており、違反すると改善命令や課徴金を払う命令が出される可能性があります。
消費者契約法では、不当な勧誘で結んだ契約を無効にする決まりがあり、ダークパターンで結んだ契約が取り消される場合もあります。
認証制度での処罰
2025年開始の認証制度では、直接的な罰則はありませんが、認証の取り消しや非認証の公表といった措置が想定されます。
これにより企業の信頼に大きな影響を与える可能性があるでしょう。
海外での例
海外では既に厳しい制裁が科されています。ヨーロッパでは、個人情報保護法違反として数百万ユーロの制裁金が科された例があり、アメリカでも政府機関による処罰例が複数報告されています。
将来的な危険性
日本でも将来的には、より厳しい法規制ができる可能性が高く、その場合は行政処分や刑事罰の対象になる可能性があります。企業は今のうちから対策をすることで、将来の危険性を避けることが大切です。
認証マークとは

ダークパターン対策協会が運営するNDD(Non-Deceptive Design)認証制度による認証マークの審査が、2025年10月から本格的に始まります。
認証マークの目的
この認証マークは、お客さんが安心してWebサイトを使えるよう、ダークパターンを使っていない健全なサイトであることを示すものです。
企業にとっては、透明性の高い事業をしている証明になり、お客さんからの信頼を得ることにつながります。
認証を取る流れ
認証を取るためには、まず企業が自分で審査を行い、その後、協会が指定する認証審査機関による一次審査受ける必要があります。
審査は、Webサイトのデザイン、使いやすさ、利用規約、プライバシーポリシーなど、幅広い項目が対象。
そして協会の企業審査局による最終審査を経て認証マークの取得となります。協会による認証審査の受付は、2025年10月より開始予定です。
認証の期限と更新
認証マークには期限が設定され、定期的な更新審査が必要になる予定です。これにより、継続的な改善と適切な運営の維持が促進されます。
認証マークの表示方法
認証を取った企業は、自社のWebサイトや宣伝材料に認証マークを表示できます。これにより、お客さんに対して信頼できるサイトであることをアピールできます。
業界への影響
認証制度の開始により、業界全体での健全化が進むと予想されます。認証を取っている企業とそうでない企業との間で、お客さんの選択に差が生まれる可能性があり、企業にとっては重要な競争要素になるでしょう。
ダークパターン 7つの分類
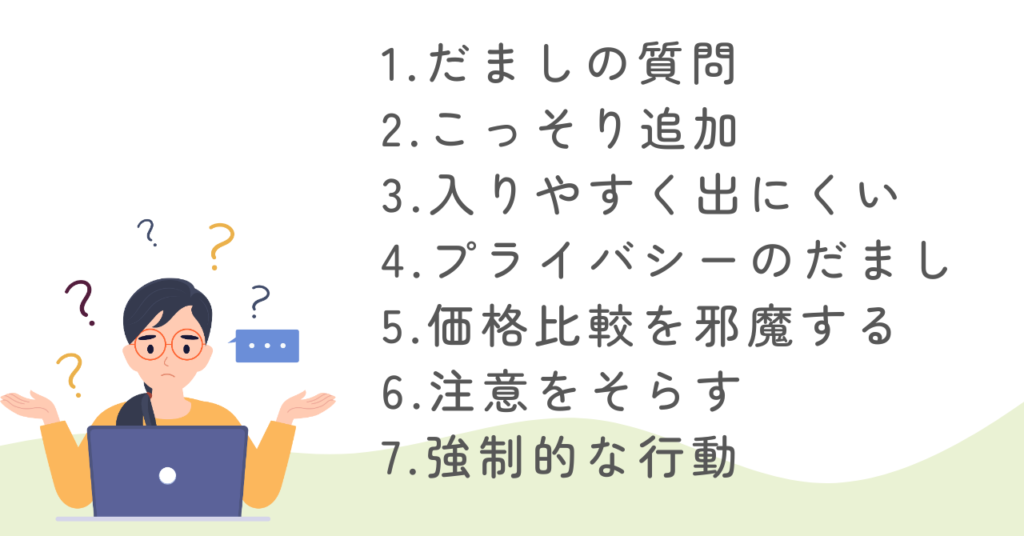
ダークパターンは、その方法によって以下の7つのカテゴリに分けられています。
1. だましの質問(Trick Questions)
質問の表現をあいまいにしたり、二重否定を使ったりして、ユーザーが思っているのとは逆の選択をしてしまうように誘導する方法です。
例えば、「メール配信を希望しない場合はチェックを外してください」といった分かりにくい表現がこれに当たります。
2. こっそり追加(Sneak into Basket)
ユーザーが気づかないうちに、商品やサービスを買い物カートに追加する方法です。
保険オプションや配送オプションなどが、ユーザーがはっきり選んでいないのに自動で追加されるケースが典型例です。
3. 入りやすく出にくい(Roach Motel)
サービスへの登録は簡単にできるが、解約や退会が異常に難しくなるように作られたしくみです。
解約ボタンが見つからない、複雑な手続きが必要、電話でしか解約できないなどの例があります。
4. プライバシーのだまし(Privacy Zuckering)
ユーザーが意図していない個人情報の共有や公開に誘導する方法です。
プライバシー設定を分かりにくくしたり、初期設定で個人情報を公開するようにしたりする例があります。
5. 価格比較を邪魔する(Price Comparison Prevention)
価格比較を難しくして、ユーザーが適切な判断をできないようにする方法です。
商品の仕様や価格体系をわざと複雑にしたり、他社との比較情報を隠したりする例があります。
6. 注意をそらす(Misdirection)
ユーザーの注意を重要でない部分に向けさせ、大事な情報を見落とさせる方法です。
派手なデザインで目を引きつつ、重要な利用条件を小さな文字で表示するなどの例があります。
7. 強制的な行動(Forced Action)
ユーザーが本来望まない行動を強制的に取らせる方法です。SNSへの投稿を強制したり、個人情報の提供を必須にしたりする例があります。
ダークパターンに該当する事例
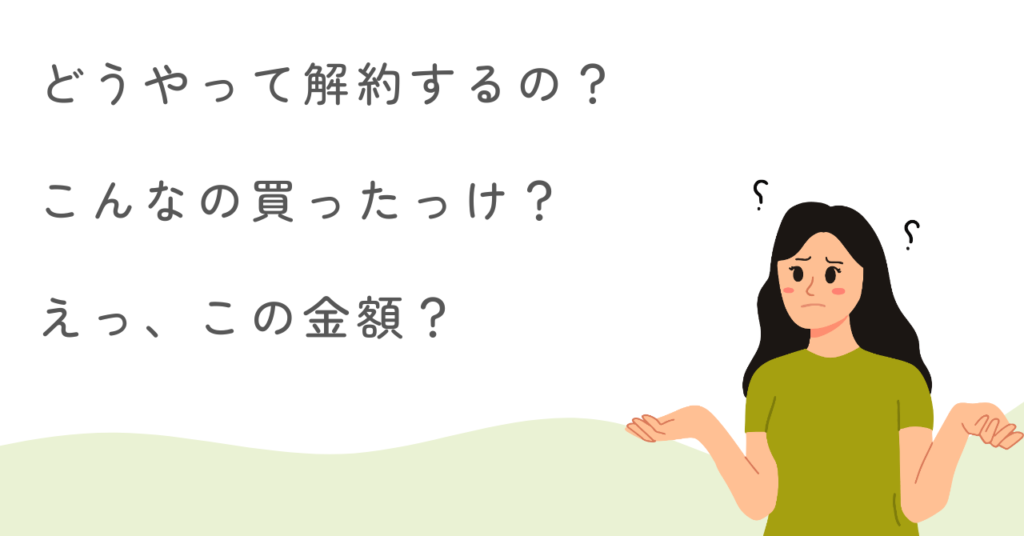
実際のWebサイトやアプリで見られるダークパターンの具体的な例を紹介します。
事例1:月額課金契約の巧妙な誘導
「初月無料」をうたう動画配信サービスで、無料期間の終了時期を分かりにくく表示し、解約手続きをメール配信停止と同じページに混ぜる。ユーザーは無料期間が終わることを忘れがちで、自動課金が始まってから気づくケースが多い。
事例2:買い物カートの自動追加
ネット通販サイトで商品を買う際に、配送保険や延長保証が自動でカートに追加され、チェックボックスが最初からオンになっている。ユーザーが気づかずに決済を進めると、いらないサービスも一緒に買ってしまう。
事例3:解約手続きの複雑化
ネットで簡単に申し込めるサービスなのに、解約は電話のみで受け付け、しかも営業時間が限られている。電話をかけても繋がりにくく、オペレーターから引き留めを受けるしくみになっている。
事例4:急がせる表示
「残り在庫3点」「あと30分で終了」などの表示を常に出し続け、実際には十分な在庫があるのに、ユーザーに急かされた買い物をさせる。タイマー表示もページを更新するたびにリセットされる。
事例5:価格表示のトリック
税抜価格を大きく表示し、税込価格を小さく表示する。送料や手数料についても、決済の最終段階まで教えない。結果として、ユーザーは実際の支払金額よりも安いと勘違いして買い物をしてしまう。
事例6:プライバシー設定の操作
アカウント作成時に、メール配信や個人情報の第三者提供に関するチェックボックスが最初からオンになっており、利用規約と同じ色・サイズで表示されるため見落としやすい設計になっている。
悪意がなくてもうっかり
ダークパターンをしてしまう事例
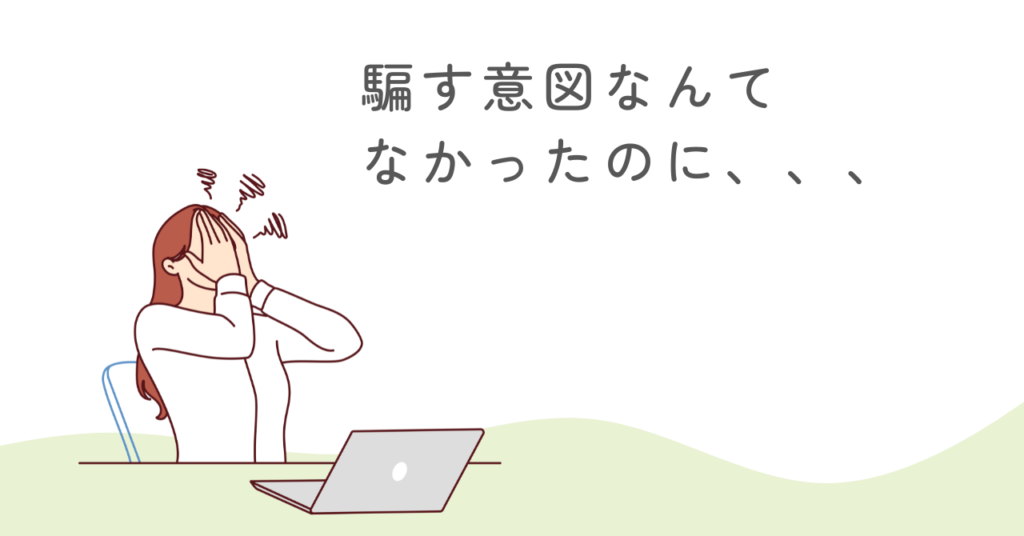
多くの企業では、悪意なく普通のマーケティング施策を実施した結果、意図せずダークパターンに当てはまる状況を作り出してしまうケースがあります。
事例1:使いやすくしようとした結果の逆効果
ユーザーの便利さを考えて、よく買われる関連商品を自動でカートに追加する機能を作った結果、ユーザーが気づかないうちにいらない商品を買ってしまうケースが発生。企業はサービス向上のつもりだったが、ダークパターンと指摘された。
事例2:デザイン統一による混乱
Webサイトのデザイン統一を図る過程で、購入ボタンと解約ボタンの色やサイズを同じにした結果、ユーザーが間違って操作してしまうケースが頻発。デザイナーは統一感を重視したが、使いやすさの観点では問題となった。
事例3:システムの制約による複雑化
古いシステムの制約により、解約手続きが複数画面にまたがる複雑なしくみになってしまった。企業としては早急にシステム改修したいが、予算や技術的な問題で対応が遅れ、ユーザーから苦情が寄せられる状況となった。
事例4:部署間の連携不足
マーケティング部門が効果的だと考えて実装した施策が、実は景品表示法に違反する可能性があることを法務部門が後から指摘。すでにキャンペーンが開始されており、急いで修正が必要となった。
事例5:海外基準の適用ミス
海外でのマーケティング手法をそのまま日本に適用した結果、日本のお客さんには馴染みのない表現やしくみとなり、誤解を招く結果となった。文化的な違いへの配慮が不足していた。
事例6:テストの弊害
成約率向上を目指したA/Bテストで、より効果的だった施策を本格導入したところ、それがユーザーを誤解させる表現だったことが後から判明。数値の改善だけに注目し、倫理的な観点での検証が不十分だった。
これらの例から分かるように、企業の意図とは関係なく、ダークパターンの問題は発生する可能性があります。
どうやって防ぐ?
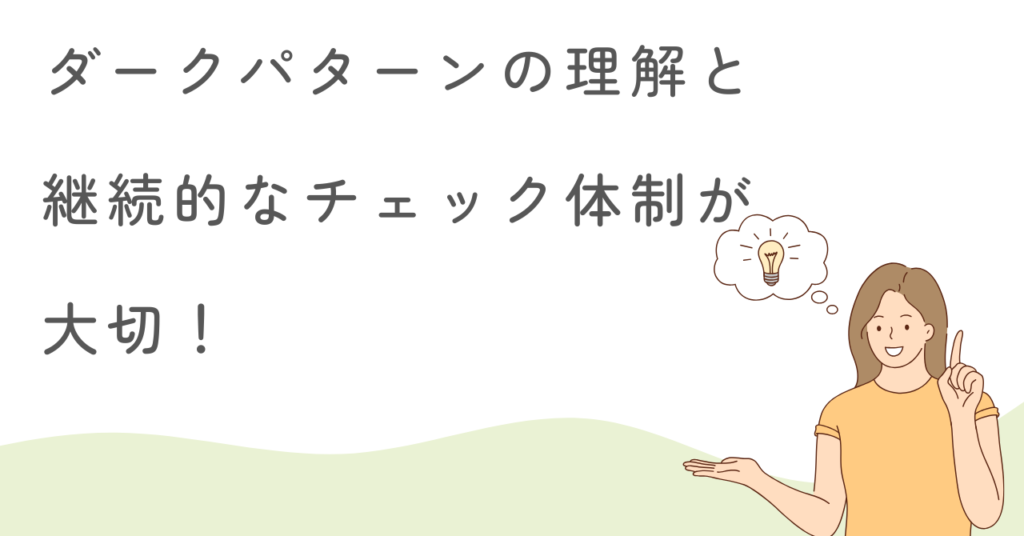
ダークパターンを防ぐためには、組織的な取り組みと具体的な実装上の対策の両方が必要です。
組織体制の構築
まず、ダークパターン対策のための専門チームや責任者を決めることが大切です。法務、マーケティング、デザイン、エンジニアリング部門の連携を強化し、定期的な会議でサイトの運営状況を確認する体制を作ります。
ガイドラインの策定
社内向けのダークパターン対策ガイドラインを作り、全従業員に周知徹底します。特に、Webサイトの制作や運営に関わる部署では、具体的な禁止事項と推奨事項を明文化したマニュアルを作成します。
定期的な監査・点検
既存のWebサイトやアプリについて、定期的にダークパターンがないかを点検します。第三者の視点から客観的にチェックするため、外部の専門機関による監査を受けることも有効です。
ユーザーテストの実施
実際のユーザーにサイトを使ってもらい、混乱や誤解が生じる箇所がないかを確認します。特に、新機能や新サービスをリリースする前には、必ず使いやすさテストを実施します。
透明性の向上
価格、手数料、契約条件、プライバシーポリシーなど、重要な情報は分かりやすくはっきりと示します。小さな文字での表記や、複雑な条件での表現を避け、一般のお客さんが理解しやすい表現を心がけます。
技術的な対策
システム面では、ユーザーの意図しない操作を防ぐための確認画面を設置したり、重要な操作には二段階認証を導入したりします。また、解約手続きは申し込みと同じくらい簡単にできるようにします。
継続的な改善
ユーザーからのフィードバックや苦情を真摯に受け止め、継続的な改善を行います。問題が見つかった場合は、すぐに修正し、再発防止策を講じます。
ここに注意!
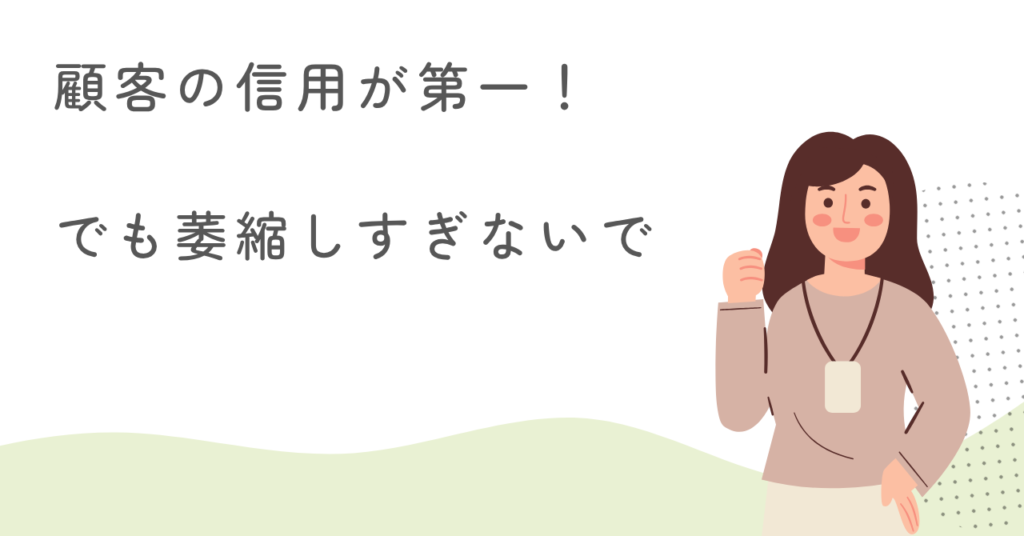
ダークパターン対策を進める上で、企業が特に注意すべきポイントを整理します。
過度な対策による機会損失
ダークパターンを避けることは大切ですが、あまりに慎重になりすぎて、正当なマーケティング活動まで制限してしまうことは避けるべきです。
お客さんにとって価値のある提案は積極的に行い、透明性を保ちながら効果的な施策を実施することが重要です。
海外展開時の注意事項
海外でビジネスを展開する場合は、各国の法規制や文化的な違いを十分に理解する必要があります。日本では問題ないとされる表現や方法でも、他国では違法となる可能性があります。
技術的な制約との両立
古いシステムを使用している企業では、理想的なユーザーインターフェースを実現することが技術的に難しい場合があります。しかし、システム制約を理由に使いやすさを犠牲にすることは許されません。段階的な改善計画を立てて、実行していくことが必要です。
従業員への教育
ダークパターンの概念や具体的な事例について、関係部署の従業員に十分な教育を行う必要があります。特に、新入社員や転職者に対しては、入社時の研修で必ず取り上げるべきテーマです。
競合他社との差別化
競合他社がダークパターンを使用している場合、短期的には不利になる可能性があります。しかし、長期的にはお客さんからの信頼を獲得し、持続可能な成長を実現できるという視点を持つことが重要です。
法的リスクの継続的な監視
規制環境は継続的に変化するため、常に最新の法的要求事項を把握し、対応していく必要があります。法務部門と連携し、定期的に法的リスクを評価することが重要です。
よくある質問

Q1: 既存のWebサイトが認証を受けられない場合、どの程度の修正が必要ですか?
A: 修正の範囲は今の状況によって大きく異なります。軽い表現の修正だけで済む場合もあれば、システムの大幅な改修が必要な場合もあります。
まずは自己診断ツールを使って今の状況を把握し、優先順位をつけて段階的に対応することをお勧めします。
Q2: 小規模なネット通販サイトでも認証を取る必要がありますか?
A: 法的義務ではないため必須ではありませんが、お客さんの信頼獲得や将来的な規制への備えという観点からお勧めします。小規模サイトでも取り組みやすい基本的な対策から始めることができます。
Q3: 企業向けサービスもダークパターン規制の対象になりますか?
A: 現在の制度は主にお客さん向けサービスを対象としていますが、企業向けサービスでも類似の問題は発生します。企業間取引でも透明性や公正性は重要であり、自主的な対応が望まれます。
Q4: 海外のユーザー向けサービスにも日本の認証制度は適用されますか?
A: 日本の認証制度は日本国内向けサービスが主な対象です。海外ユーザー向けには、各国の規制に応じた対策が必要になります。
ただし、グローバルに統一された基準を採用することで効率化を図ることも可能です。
Q5: 認証取得にかかる費用と時間はどの程度ですか?
A: 具体的な費用や審査期間は制度開始時に発表される予定です。ただし、中小企業でも取得しやすい料金設定になる見込みです。審査準備を含めて数ヶ月程度の期間を想定しておくことをお勧めします。
Q6: 一度認証を取れば永続的に有効ですか?
A: 認証には有効期限が設定され、定期的な更新が必要になる予定です。これにより、継続的な改善と適切な運営の維持が促進されます。
健全なサイト運営をする上で大切なことは
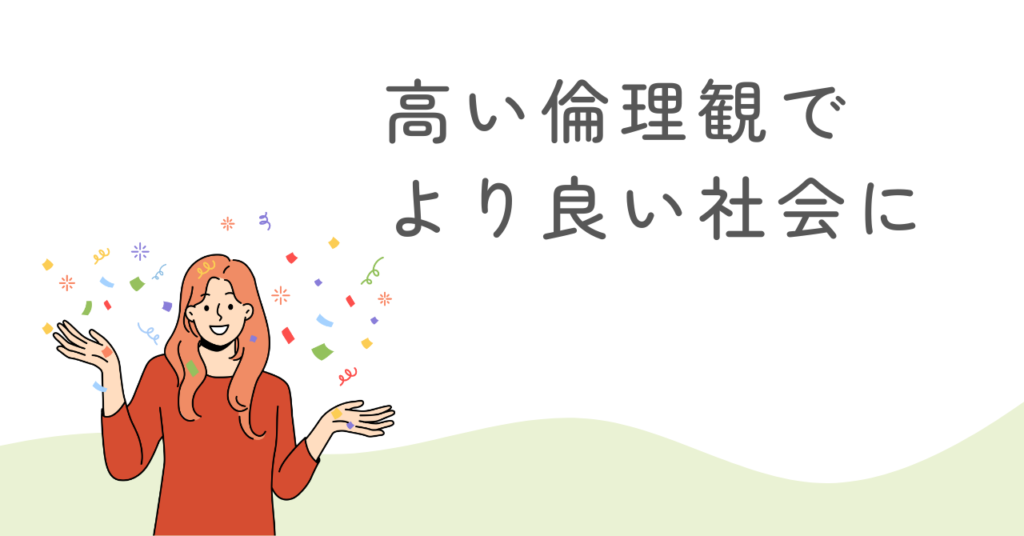
健全なWebサイト運営を実現するためには、単にダークパターンを避けるだけでなく、より根本的な考え方の転換が必要です。
ユーザー第一の考え方
最も重要なのは、短期的な利益よりもユーザーの便利さと満足度を優先する考え方です。ユーザーが本当に必要としているサービスや情報を提供し、透明性の高い取引を心がけることで、長期的な信頼関係を築くことができます。
持続可能なビジネスモデル
ダークパターンに依存したビジネスモデルは長続きしません。正当な価値提供に基づいたビジネスモデルを構築し、お客さんが進んでお金を払いたいと思えるサービスを提供することが重要です。
組織文化の醸成
全社的に倫理的なビジネス運営を重視する文化を育てることが必要です。売上目標の達成も重要ですが、それが不正な手段によって達成されることがないよう、適切な管理体制を構築します。
継続的な学習と改善
技術の進歩や規制環境の変化に対応するため、継続的な学習と改善を行う体制を整備します。業界の動向を常に把握し、良い事例を積極的に取り入れることが重要です。
関係者との対話
お客さん、従業員、株主、監督官庁など、すべての関係者との健全な関係を維持します。透明性の高いコミュニケーションを心がけ、問題が発生した場合はすぐに対応します。
社会的責任の自覚
企業活動が社会全体に与える影響を認識し、社会的責任を果たすことを重視します。ダークパターンの排除は、単なるリスク回避ではなく、より良い社会の実現に貢献する活動として捉えることが重要です。
ダークパターン規制の開始は、企業にとって新たな挑戦である一方、より透明で公正なデジタル環境を作る絶好の機会でもあります。早期の対応により、お客さんからの信頼を獲得し、持続可能な成長を実現していくことが、現代の企業に求められる重要な課題といえるでしょう。
まとめ
ダークパターンは一時的な売上につながっても、長期的には顧客離れや企業イメージの低下を招きかねません。
今こそ、ユーザーに誠実なサービス設計へと見直す好機です。認証マークの導入や法規制の流れをチャンスと捉え、信頼されるサイトづくりを進めていきましょう。
ユーザーとの信頼関係こそが、あなたの企業の持続的な成長の鍵になるはずです。
※ダークパターン対策ガイドライン・自己審査チェックシート・NDD認定制度要綱 ダウンロードページ(一般社団法人ダークパターン対策協会)は「こちら」からご覧いただけます。